山田豊文先生3月1日特別講演 8月22日に延期のお知らせ
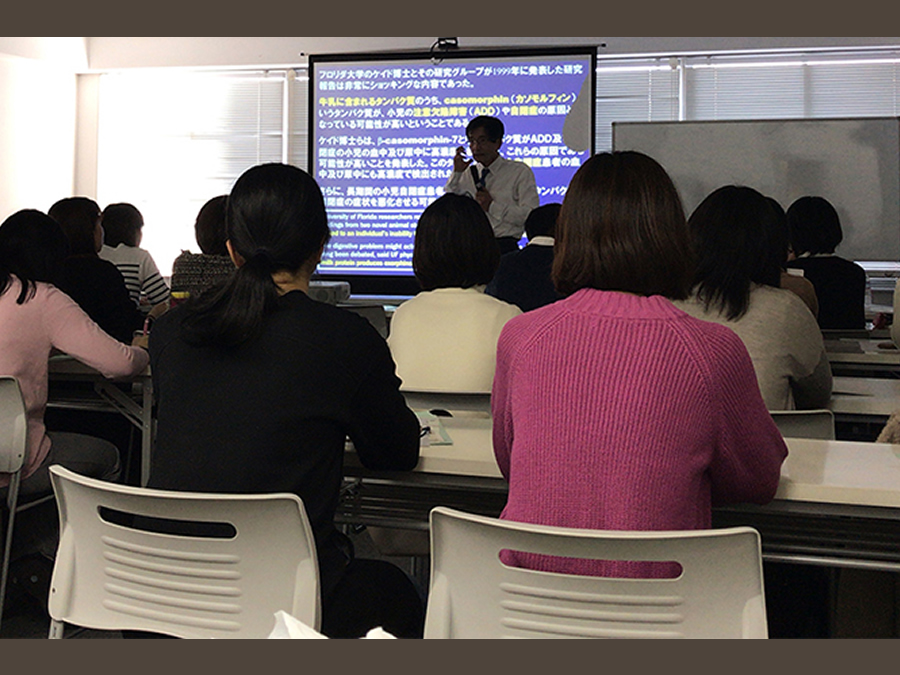
~3月1日(日)山田豊文先生ご講演 8月22日に延期のお知らせ~
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
この度、3月1日(日)品川にて開催を予定しておりました山田豊文先生のご講演でございますが、新型コロナウィルスの影響により開催を延期することとなりました。
実施に向け鋭意努力をしておりましたが、
移動や会場における、不特定多数の方と接触することで起こる感染リスクはもとより、
万一発症者が出た場合の皆様におかけするご心配やご迷惑などを考慮し、
一旦延期として事態が収束するのを待つ方が皆様にとって今できる我々の最善ではないかと、弊社(子どもの発達デザイン研究所)および杏林予防医学研究所 二社間で協議した結論でございます。
心待ちにされている皆様には、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、
深くお詫び申し上げますと共に、何卒ご理解ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。
なお、代替の日程につきましては、
8月22日(土)13時~15時
場所は同じく品川シーズンテラスカンファレンス アネックス棟3階ホール
を予定しております。
ご購入いただきましたチケットは、そのまま8月22日にご使用下さいませ。
8月にご都合がつかない方は、次々回以降の開催時にご利用いただければ幸いです。
(恐縮ながら延期のため払い戻しについては行っておりません。何卒ご容赦くださいますよう、お願い申し上げます。)
2020年2月18日
主催:子どもの発達デザイン研究所
問い合わせ先:info@kodomodesign.or.jp